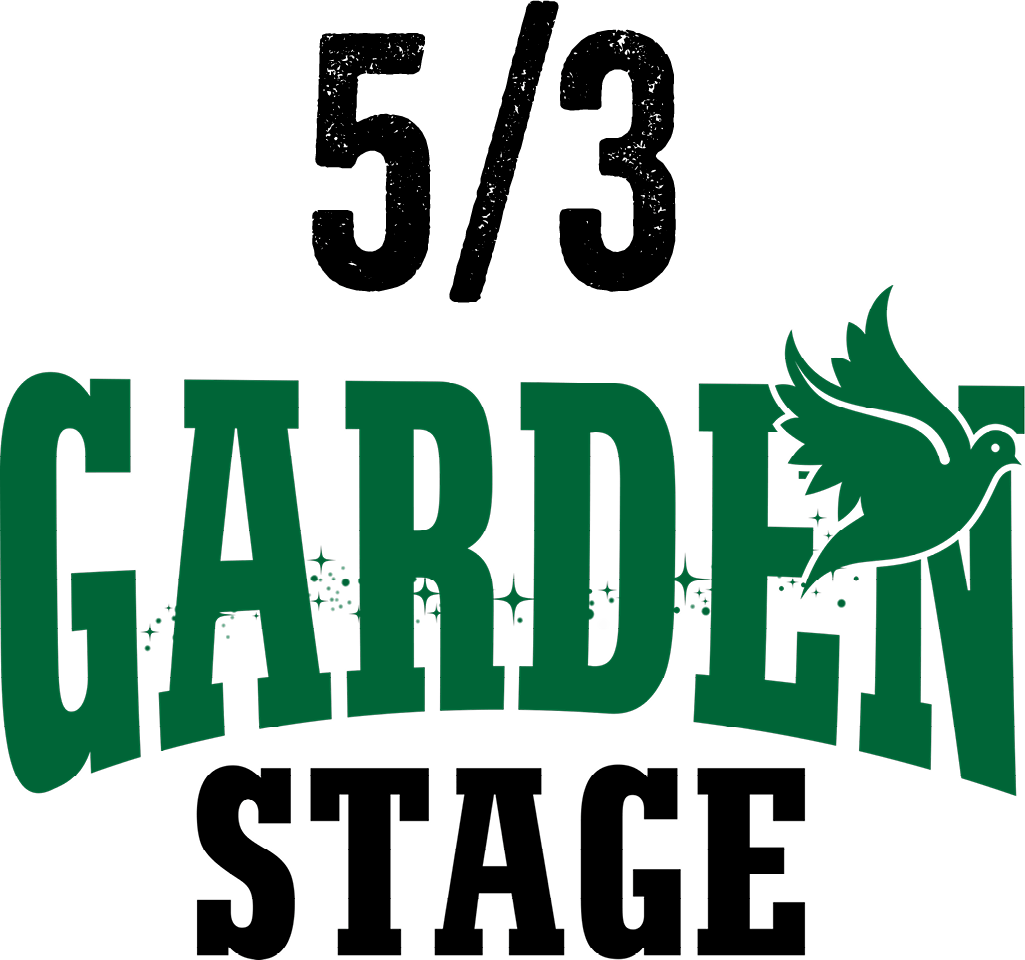
総括レポート
4年ぶりに蘇った自由の庭!
すべての遊び方に線を引かず、
誰にも開かれた音楽広場へようこそ

暑いくらいの快晴に恵まれたビバラ初日、ビアガーデンもフードエリアも終日大賑わいだったVIVA LA GARDEN(通称:ガーデン)。「もうひとつのビバラ」である入場無料のこの屋外エリアは、コロナ禍で開催できなかった期間を乗り越え、4年ぶりの復活となった。VIVA LA ROCKのチケットを持っていない人でもふらりと訪れて楽しむことができるガーデンは、だからこそ、新たな音楽ファンを増やす可能性に満ちた場所でもあり、新しい楽しみ、新しい音楽に出会う場所でもある。そして誰に対してもオープンで街と共存しているからこそ、音楽カルチャーが根付いていく土壌を作ることもできる――そういう意味でガーデン復活はビバラの本願成就であり、この大賑わいこそがビバラの完全復活を意味していると言ってもいいだろう。
ゆるキャラショーやお笑いライブ、ワークショップやキッズのための「あそビバ」に加え、ティラノサウルスレースも実施されている今年のガーデン。多彩な催しと老若男女と恐竜とが入り混じって、初っ端からピースな遊び場が完成していた。そんな幸福な空気の中で行われるGARDEN STAGEのライヴの数々は、ビバラでありながらビバラの外へ飛び出すような初めての出会いを多く生み出す音楽空間になっていく。ビバラの扉でもあり、音楽そのものへの扉でもあるのがGARDEN STAGEの大きな意義だ。

トップバッターとして登場したのはAmber’s。豊島こうき(Vo&Gt)と福島拓人(Gt&Programming)からなるユニットは、歌謡曲から連なるJ-POPのメロディと、ブルースやR&Bを背骨にした音楽がガシガシとぶつかり合うようなライヴを披露した。<広げて その翼を>(“We Wish on a STAR”)という通りの飛翔感に満ちたメロディを超ハイトーンな歌声で飛ばし、雄大なギターフレーズとコーラスがその歌をさらに大きくたおやかに聴かせる。
続いて昭和歌謡的な歌と小気味いいリズムが印象的な“Desire -欲情本能-”、ラテンと歌謡が湿った質感で混ざり合う“Question”を立て続けにプレイ。さまざまなボーダーを超えている豊島の圧倒的な歌があるからこそ、メロディ一発で音楽を自由に旅できるのだろう。根底にはブルージーなものがありつつ、しかしジャンル無視の音楽を奔放なステージワークで歌う、鳴らす、ぶつける。一聴すると洒脱な音楽だが、泥臭いほどに客席を煽り、ともに行くことを求め続ける豊島の姿が印象的だ。その歌とサウンドの透明感ったらないが、その飛ばし方はひたすら泥臭い。“DRIVE”では観客にタオル回しを執拗に求め、さらには福島がコッテコテのギターソロを披露し、その優雅なギターを切り裂くようにハイトーンの<アァー!>がインサートされる。この歌だからどんな音楽でもモノにできると同時に、どんな端正な楽曲もこの声が突き抜けてしまう瞬間があって、それをふたり自身が面白がっているんだろうなと感じるライブである。
「今日、夢がひとつ叶いました。ビバラはすごく特別で、拓人と初めて一緒にライヴに行ったのがこのフェスでした。だから、いつかこのステージに立ちたいと思って活動してきました。最初は二人だけの目標だったのに、俺達以上に喜んでくれる人がいると、この何年かをこの日のために頑張ってきたんだなと思えます。……僕はみんなの中心にいるような人間じゃなくて、世界の隅っこで捻くれているような人間です。でもこうして音楽を通じて出会ってくれる人がいるのなら、胸を張って『隅っこからでもできることがある』と言えます」(豊島)
そう話し、白と黒のどちらでもない場所に属してきた自分の孤独を吐露する歌を打ち上げてステージを降りた。孤独で、だからこそ強くなりたいと願う。自分を諦め切れない気持ちがズシリと伝わる1曲だった。

続いて登場したのは森 大翔。16歳の時に「Young Guitarist of the Year 2019」(16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会)に出場し、世界一を獲得した超絶技巧のギタリスト・シンガーである。それを長々と説明するより先に、ステージに上がるや否や怒涛の早弾き連打で「こういう者です」のご挨拶。実際、客席を見渡しながらギターで語りかけるようにプレイするのが印象的だ。“台風の目”では、叩きつけるような(しかし正確無比な)ギターさばきを見せる。さらに、弱さや言い訳と向き合って己の首根っこを掴むような歌を衝動的にぶつけていく。ギター修行僧とでも言いたくなるようなストイックさがある。そしてそれと同時に、時折見せる笑顔やメロディには愛嬌も滲んでいて、ただソリッドで凄まじいだけではない、自然と近さを覚えてしまう親しみやすさ、純粋な楽しさが前に出てくるのが彼の大きな力だ。
「めちゃくちゃ楽しいです。やっぱり音楽は楽しいですね。なので、ビバラの大きな舞台だからこそ音楽の挑戦をしたいと思っていて。この場で録音したすべての音を回してくれるルーパーを使って演奏して見たいと思います。もちろん自分の失敗も回してしまうシビアな機械なんですが、今日に向けて練習してきたので、頑張ります」
観客「頑張ってー!」
「頑張る!」
観客「楽しんでー!」
「楽しむ!」
そんな対話が自然と繰り広げられ、ステージ上の音だけではなく目の前の人間との呼応が怒涛の音、矢継ぎ早な歌になっていくのが面白い。弾き語りライヴということも大きいかもしれないが、それにしても歌と人の距離、声とギターの距離、メロディと心の距離がとても近い。
“最初で最後の素敵な恋だから”は素直で衝動的で蒼いメロディが印象的なラヴソングだが、突如爆速のギターソロを叩き込み、カノンのフレーズを歌とギターでインサートするユーモラスなアレンジにニヤリとする一幕も。音楽が楽しい!という言葉に偽りなし、これでもかと言わんばかりに音で遊びまくっているアクトだった。次の6月9日に20歳を迎えること、その直前の5月31日にファーストアルバムをリリースすること、20歳の抱負は「素敵な30歳になること」なのだとささやかな未来を語ること、そして「自分に厳しめの曲をやって終わります」と言って披露したラストナンバー“剣とパレット”では自分の限界に挑むような超絶プレイを繰り出し続けたこと--仏像を彫るような極限の集中状態、しかし緊張感の中から緩やかに滲んでくるユーモア。そのバランス感にこそ感嘆する、大器のビバラ初見参だった。

3番手に登場したのは、Hakubi。片桐(Vo&Gt)の「VIVA LA ROCK 2023、楽しんでますか? 私達とここで出会ったこと、自慢にさせてみせます」という言葉から雪崩れ込んだ“ハジマリ”は、この曲を作った当時こそ、片桐の無限の自己嫌悪からの脱却を願う歌だった。しかしこの開放的な場所で鳴らされることで、そしてコロナ禍に押し込められ続けた数年を経たことで、ようやく掴んだロックの自由を掲げるファンファーレのように感じられるから不思議だ。実際、片桐が発した「やっと戻ってきたね」という声は、メジャーデビューを階段にしていざ駆け上がろうというタイミングでコロナ禍に道を塞がれ続けたHakubiや多くのロックバンドが、この数年の苦渋のすべてをようやく乗り越えんとする瞬間を映したものだったと思う。
180度すべてを見渡しながら、一人ひとりを指さしながら、強い視線を向けながら、徹底的に目の前の人に向き合う片桐。ダメな自分、嫌いな世界、気にくわない人生に呻きながらもなんとか明日を迎えんと叫ばれる歌は、まさにあなた自身のことでもあるんだと伝えようとしているようで。そんな愚直で泥臭い歌が連打されていった。今この一瞬だけではなく、ここに至るまでのストーリーまでを鮮明に映すようなライヴだからこそ、“夢の続き”を歌う説得力と重みが生まれるのだ。<僕らはまだ終わっていないよ>という一節は、この楽曲が生み出された当時よりも大きな意味と実感でもって、「あなた」に刺さったことだろう。
そこから矢継ぎ早に演奏された“在る日々”も、終わってしまいたい心を乗り越えるための始まりの歌である。“光芒”も、<いつかは>という願いを諦め切れないと気づいては明日のほうを向こうとする歌である。かきむしるようにギターを弾く、歯を食いしばってギリッとした表情を見せる、そうやって目に見えない何かを切り刻みながら「届け」と叫ぶHakubiの歌は、苦しんでもがいて転げ回っている最中を映し出すドキュメントとして強烈なリアリティを持っている。そこに生まれるのは安易な共感ではなく、ただただ「生きている」という実感だけ。それがいいし、それだけをぶつけたくて叫び続けるバンドなのだと感じるライヴだ。「上手くいかないこと、悲しいこと、どうしようもないこと。全部、音楽でぶっ壊したいよな」と片桐は叫んだが、Hakubiは「私達が壊す」でも「私達が代弁する」でもなく、「壊したい」とだけ言う。どこまで行ってもこの歌は願いであり、まだ掴めない理想の歌である。だからこそ、ステージ上の3人とフロアの人間との間には線がない。
「最後の曲は、コロナ禍で作った曲。去年のビバラでも歌った曲です。ずっとひとりで寂しかった日々。私って生きている意味あんのかなって思ってしまう、あっけない日々の中で作りました。そこから1年経って、みんなで声を出せる今こそ、この曲を完成させたいと思いました」(片桐)
そう言って鳴らされた“悲しいほどに毎日は”では、あの頃は願いのようだったシンガロングが現実のものとして響き渡った。あっという間に終わって行く1日なのは変わらない。変わらないけれど、確かに自分以外の人間の声と愛と命があるのだと実感できる一瞬だっただろう。実際、それだけの喜びが端々まで満ちているライヴだった。

GARDEN STAGEラストを飾ったのは、ロックDJとして初回からこのガーデンを数々のロックアンセムで彩ってきた片平実(Getting Better)。今年はなんとゲストヴォーカルが次々に登場! オープニングナンバーは片平自身のオリジナルプロジェクトである「Garas」の“Fly”という楽曲で、岩手県宮古市出身のシンガーソングライターである村松徳一が歌唱。そこから日本のロックの名曲たちを次々にスピンしつつ、タクマ(コロナナモレモモ)、今村力(Jam Fuzz Kid)、岩渕想太(Panorama Panama Town)、御厨響一(鋭児)、さらにはCAVE STAGEのトリを務め、最高に熱い「ロックバンドの遊び方」を体現したTHE KEBABSのライブ終わりで駆けつけた佐々木亮介(a flood of circle/THE KEBABS)を呼び込み、その音に誘われて集まってきた人達も巻き込んでロックパーティーを繰り広げていった。
これ、つまりはDJとしてプレイしていく楽曲に当の本人が登場して歌うわけで、そんなことをされてしまったらどうしたって盛り上がらないはずがないのだけど、それ以上に「俺の仲間を全員呼びました、だからあなたも隣のヤツとの線をなくして遊んでいって!」という片平自身のピュアな想いとロックパーティーの本質たるメッセージが、言葉ではなくそのプレイ自体から、そしてその場の熱狂から、ぐんぐんと伝わり体現されていったのが何よりも最高だった。初日の締めにふさわしい、とても素敵なロック大号令だった。
テキスト=矢島大地
撮影=古溪一道





