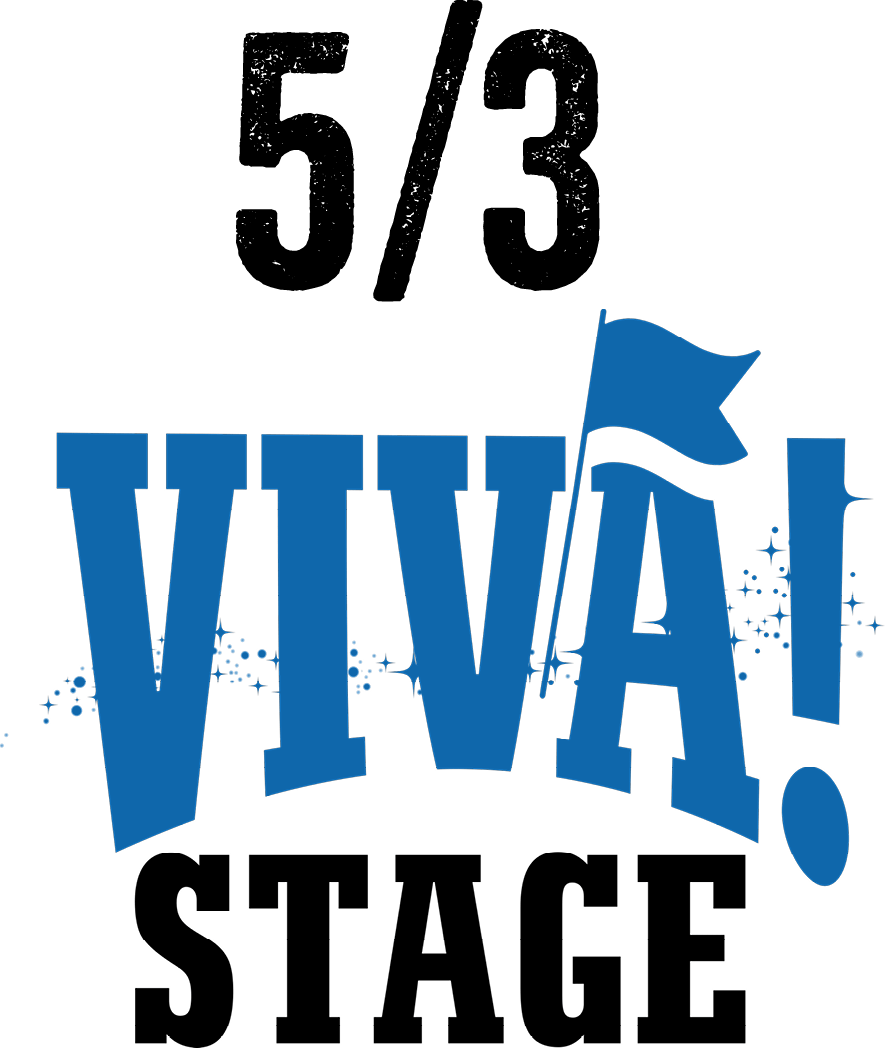
総括レポート
フェスの歴史とアーティストの歩み
それぞれの想いが交わり生まれた
10回目のビバラ初日の光景

「自由に楽しんでいただけるフェスを開催することができました!」
プロデューサー・鹿野 淳の開会宣言に大歓声が応える。過去3年間にわたり、配信での開催やさまざまな制限付きでの開催を余儀なくされ、それでも最善を模索しながら止まらずに進んできた「VIVA LA ROCK」だけに、ほぼ本来の姿を取り戻した形のフェス開催を迎え、ステージの上も下も感慨はひとしおだ。ほどなくして1組目の登場を告げるジングルが鳴り出して、ボルテージはまた一段と上がる。

今年で10回目の節目を迎えたビバラ、5日間にわたる祭典の火蓋を切ったのは岡崎体育だ。バンバン炎の打ち上がるステージにひとり仁王立ちして両手を広げる彼の、パーカーにジャージという出立ちは完全に「ちょっとコンビニへ」だが、醸し出す風格は完全にスターのそれである。先日リリースされたばかりの“Knock Out”からライブをスタートさせ、メタリックなぶっといビートの連打に派手なシンセ、アグレッシヴな音で強烈な「目覚まし」を仕掛けていく。<フィジカル全振りMPは0>という、フェス参加者のモードに通じるリリックもこの場にピッタリだ。
バキバキのEDMサウンドにラップを乗せ自己紹介をかます“Open”から“R.S.P”へ。「全員踊れ!」との檄に両手を挙げた観客たちが応え、アリーナが震える。曲中でおもむろに「ジャンケンで勝った人だけ踊って良いコーナー」が始まったり、“Call on”で無茶なコール&レスポンスを振ってみたりといった遊び心も含め、とにかく多方向から徹底的に楽しませ、巻き込んでしまうそのエンターテイナーぶりは随一。スクリーンに映る観客は誰もがみんな笑顔だ。
MCでは、ビバラ出演は2回目だが、会場の中でライブをやるのは初めてであることを語る。前回出演時には「たまアリでワンマンをやるまで立ちたくない」という理由で屋外ステージに出演したという彼にとって、たまアリワンマンを有言実行で成功させた上で挑むこの日のライブは、凱旋のステージでもあったのだ。そんなストーリーを受けて5日間全体のトップバッターという大役をオファーした主催側と、ライブで応えてみせる岡崎。信頼関係の透けて見える一幕だ。パンクロック調のトラックで突っ走る“なにをやってもあかんわ”から、ラストに“The Abyss”を投下。アンビエントなテクノサウンドから、カラフルに爆発する後半へ至る多幸感たっぷりの展開がたまらない。大写しとなった「BASIN TECHNO」の文字とともに会場全体を存分に踊らせまくった彼の、「VIVA LA ROCK、俺が持って帰ってきました、岡崎体育でした!」という去り際の発言は、決して大袈裟ではなかった。

「リハから本気出しますけど、いいですか!」(ヨコタシンノスケ・Key&Vo)
サウンドチェックの段階から“MEGA SHAKE IT!”、“推しのいる生活”をハイテンションで演ってみせ、振り付けまでしっかりやるのがキュウソネコカミ流。あらためて登場後、「数年ぶりの本来の盛り上がり、見せてくれるんか、ビバラ!」とヤマサキセイヤ(Vo&Gt)が吼え、“ウィーワーインディーズバンド!!”のファスト&ラウドなバンドサウンドを炸裂させていく。間髪入れずに雪崩れ込んだのは“ビビった”。ソゴウタイスケ(Dr)による緩急自在なビートに乗って、お立ち台に乗ったカワクボタクロウのベースが唸りをあげ、オカザワカズマがキレキレのギターリフを決める。
「ライブハウスやフェスに声が戻ってきてる象徴みたいな曲、俺たちがやっていいですか!」と繰り出したのは、これまで数々の現場を踊らせてきたキラーチューン、“ファントムヴァイブレーション”だ。荒々しく突っ走るライブ感たっぷりなスタイルながら 決めるべきところはきちんと決めるテクニカルさも持ち合わせるキュウソの演奏を、観客たちはステップを踏み、手を振り、声を張り上げて全身で楽しんで受け止めている。そんな様子を前にしたセイヤ、「これがやりたかった! ロックバンドのライブ楽しんでいってくれ!!」と絶叫。
中盤には“ひと言”をライブ初披露。スクリーンに歌詞を出しながらの演奏だが、仮にそれがなくともはっきりと聞き取れるような歌い方で、SNS時代にあって誰しもが感じたことのあるだろう違和感をセイヤの視点から言葉にし、正面から伝えていく。淡々とした演奏と歌に差し込まれる嵐のようなディストーションサウンドも鮮烈な印象を残した。ビバラの10年の歩みを讃えつつ、呼ばれなかったり呼ばれたり、悔しい思いもしたり……と思い出を振り返った後は、「この曲をやれるのを3年待ち侘びてました」と“DQNなりたい、40代で死にたい”をぶっ放した。セイヤは気迫のシャウトを繰り返し、マイクスタンドを薙ぎ倒して寝っ転がったり。終盤には<ヤンキーこわい>のコール&レスポンスを背負ってフロアに突入すると、オーディエンスに支えられながら歌い切ってウォール・オブ・デスを創出。それはライブシーンの再生を実感させる光景だった。

まだ午後に入ったばかりだというのにムンムンと熱気の立ち込める場内へと登場した、VIVA! STAGEの3組目はKEYTALKだ。首藤義勝(Vo&Ba)の歌はじまりで“桜花爛漫”が鳴り始めた瞬間、飛び跳ねて歓喜するオーディエンスたち。レクチャーするまでもなく合いの手もバッチリ入れていく。一音鳴った瞬間に盛り上がりのスイッチが入る曲をいっぱい持っているのがKEYTALK。そして彼らはそういう曲をずらりと並べて今年のビバラに挑んできた。
所狭しと動き回り、盛り上げ役を務めながらも細やかなフレーズを正確に生み出していく小野武正(Gt&Cho)に、華のあるプレイと正確無比なリズムを両立させる八木優樹(Dr&Cho)。伸びやかな歌声を響かせながらそれぞれの演奏にも余念がない寺中友将(Vo&Gt)と首藤。彼らのツインボーカルが爽快で、ファンキーなカッティングやスラップベースも踊る“MATSURI BAYASHI”では、各パートのソロも盛り込んで喝采を呼ぶ。埼玉出身のメンバーを擁し、前身バンドも埼玉で結成したという歴史を持つ彼らだけあって、MCでは初期から出続けているビバラへの祝福と、集まってくれる観客たちへの感謝も忘れない。
ステージ上とアリーナ頭上の2機のミラーボールが回る中演奏された、4つ打ちダンスロックにお祭り感をプラス、ラップ調のパートなど遊び心を交えた……つまりKEYTALKの専売特許のような曲調をネクストステージへと押し進めた感のある“君とサマー”に続いては、優しいアルペジオに乗せた巨匠のファルセット混じりの歌い出しで“バイバイアイミスユー”が来た。徹底的な楽しさの間に差し込まれる美メロでしっとり聴かせる、こういう術も持っているのがKEYTALKである。……とはいっても、彼らはやはりフェスのお祭り感を体現する存在だ。タフなビートと軽やかなギター、トリッキー極まりない曲展開で絶え間なく攻め立てる“Summer Venus”、そして「待ってました」の“MONSTER DANCE”へと至る全7曲を、体感15分くらいで完遂。展開も照明も観客たちのリアクションも、全てがド派手でとびきり痛快な宴を終え、にこやかにステージを去っていった。

アイリッシュなSE“RUN RUN RUN”に湧き上がる手拍子、go!go!vanillasが登場する。まずは多声のコーラスが印象的な始まりから、ヘヴィに歪ませたギターと軽やかなヴァイオリンの音色、郷愁を誘うメロディが一体となって押し寄せる“HIGHER”。「さあ、ロックンロールパーティー始めようぜ!」ニヤリと笑いながら牧達弥(Vo&Gt)が告げ、“平成ペイン”に繋ぐ。長谷川プリティ敬祐(Ba)と柳沢進太郎(Gt)がステージ両端へと進み出て、ステージ全体を大きく使ってのプレイ。耳から身体へと作用する、カラフルでダンサブルなロックンロールの破壊力だけでなく、立ち上がりながら猛然とビートを刻むジェットセイヤ(Dr)を筆頭に、とにかく全員の動きがでかい上に楽しさが全面に滲み出ているから、視覚面からもどんどん惹きつけていく。
「俺たちもインディーズデビューから10周年。一緒に歩んできたと言っても過言ではない」とビバラへの想いを口にしてから、「今日イチ、とびきり青いやつをいこう」とドロップした“青いの。”は、瑞々しく弾むポップなサウンドに乗って、牧がハンドマイクでフロアに近づきながら歌う。ご機嫌なワウギターが導く“エマ”、炎が打ち上がる中で疾走した“カウンターアクション”と、ライブで映える楽曲が立て続けに演奏され、しかもほとんど曲間を空けないという攻めのライブを目の当たりに、フロアは終始波打ち続けている。楽曲ごとにアプローチは違えど、ロックの歴史へのリスペクトと理解度の高さが垣間見えるのがバニラズの美点の一つだ。
「やっと俺たちのフェスが帰ってきたなって実感を、ひしひしと今日感じてます」「ここにいる全員の人生が最高のものになりますように」。そう牧が告げ、ラストの“LIFE IS BEAUTIFUL”へ。冒頭、<君となら ビバラとなら>と歌詞変えてロングトーンを響かせる牧の姿に大歓声が上がり、サポートの井上惇志 (showmore)が奏でる鍵盤やホーンの音色も交えた高速モータウンビートが祝祭感たっぷりに轟いたのだった。そうそう、演奏を終えてステージを降りようとする彼らに、「同期の」ビバラチームからインディーズデビュー10周年を祝う花束が贈られたことも記しておきたい。

狭義のロックフェスにはとどまらないという姿勢を早くから打ち出してきたフェスがビバラだとすると、その象徴となる一人がSKY-HIである、という認識に異論は少ないはずだ。自身のハウスバンド「THE SUPER FLYERS」からSQUADとしてギターTak田中・ドラム望月敬史・DJ HIRORON、そしてKensuke、Money、TAK-YARD、JUNからなるダンサー陣「BLUE FLAP QUARTET」を従えての彼のライブは、オープニングの段階からド級の重低音でアリーナを揺るがして始まった。黒の衣装を翻しながらダンサーとともに舞い、“Mr. Psycho”の狂気をまとったトラックへ矢継ぎ早に言葉を乗せていく。続いては最新アルバムからの“Happy Boss Day”。この曲をはじめ比較的新しい楽曲の多いセットリストで、しかも生音ありとはいえこの日の出演者中では異質なサウンドで爆発的な盛り上がりを呼んでいるこの光景こそ、SKY-HIとビバラの歩みを雄弁に物語っているではないか。
2017年に初めてビバラに出た時はガラガラだった、以前から親交が深くビバラのステージも共にしたことがあるたなか(Dios、ex. ぼくのりりっくのぼうよみ)の結婚式に昨日出た──というエピソードを祝福と冗談を交えつつ披露した後、「すごくハッピーでポップでキュートな曲です」との曲振りから“何様”を披露。紅く染まったステージから、荘厳でディープなサウンドが轟き、攻撃的なリリックが速射砲のような高速ラップで浴びせかけられる。さらに「新しい友達も今日は呼んでるぜ」との言葉を受けてステージに現れたのはAile The Shota。彼の柔らかな声色にオートチューンをかけたボーカルと、エッジの効いたSKY-HIのラップが交差し溶け合う“Tiger Style”は、なんとも気持ち良い。
アンセミックな曲調にDJやギターのソロ、ドラムVSラップの掛け合いも盛り込んだ“Double Down”から、アリーナを文字通り震撼させるハイテンポのビートにぶち上がった"D.U.N.K."、自身の事務所・BMSGのアーティストたちの名を挙げてから、彼らに捧げた“MISSION”とライブは進み、再びガラガラのビバラを振り返りながら、そんな自分が間も無くアリーナツアーに出ることにも言及、“To The First”を高らかに歌った。そして当時の自分と同じような気持ちを抱えるあらゆる人々を、でっかい肯定でまるごと包む“The Debut”でフィニッシュ。「おい、生まれてきてくれてありがとうな!!」。SKY-HIの激しくも優しいシャウトが胸に残った。

初日も大詰め、VIVA! STAGEのトリを飾るのはTHE ORAL CIGARETTESだ。デジタルなSEと乱れ飛ぶレーザーに迎えられながら悠然とスタンバイ。挨拶がわりの「一本打って~」を生演奏でぶつけたあと、金属的なノイズを帯びた爆音を炸裂させ、“Red Criminal”からライブをスタートさせた。曲中、「この曲、もっと盛り上がってほしくてやったんですけどね?」と不敵に煽る山中拓也(Vo&Gt)の言葉に、アリーナ全体が軽々と沸点を超えていく。
「ちょっとマイナーな曲もやっていきます。ついてこれるやつ、どんどん来いや」との宣言通り、2曲目は“キエタミタイ”という意外な選曲。この曲や“mist...”のように活動初期からの楽曲から最新曲”Enchant“まで、あらゆる時代の曲が並んだセットリストは、初回から出ているというビバラへの愛ゆえだろうか。ひとつたしかに言えることは、「鹿野さんに怒られながらステージに立ってました」という彼らが今や、ビバラと同じさいたまスーパーアリーナでワンマンを行うまでに成長を遂げ、大観衆を前に自在で堂々たるパフォーマンスをしているという現在進行形の事実だ。
“カンタンナコト”では、「今日は来ないはずだったんですけど、なんか袖におったから呼ぶわ」と悪戯っぽく紹介されたSKY-HIが登場。黒髪・白衣装の拓也と金髪・黒衣装のSKY-HIがステージ上で入り乱れながらマイクを握る様は実に絵になる。中盤で披露した“BUG”の、ドラムンベース調のデジタルなサウンドはライブ映えしないわけがないと思っていたが、実際に制限のない現場で初めて聴く同曲は、解き放たれた獣のように場内を席巻。続く“Tonight the silence kills me with your fire”でも流れは続き、鈴木重伸の鋭いギターと、怪しく蠢くあきらかにあきらのベース、中西雅哉の踏み鳴らすビートを存分に浴びて、場内は最早カオティックな様相を呈してきた。
これまでもキラーチューンであり続けた“狂乱 Hey Kids!!”で広大なアリーナを完全制圧したあと、最後に「今日はほんまにありがとう!」「これからもよろしく」という言葉そのままの“LOVE”を贈ったオーラル。クラップと大合唱に包まれながら、VIVA! STAGEはピースフルに初日の幕を下ろした。
文=風間大洋
撮影=小杉歩





