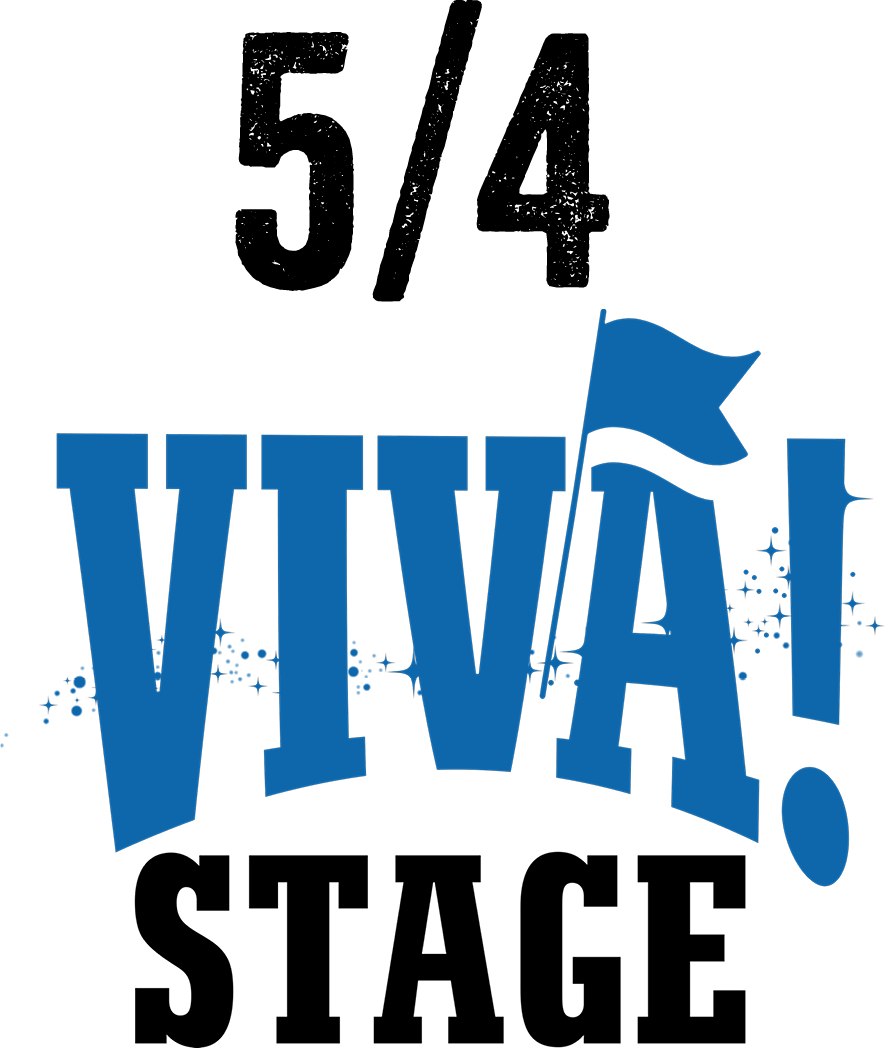
総括レポート
これぞVIVA LA ROCK
それぞれの流儀で会場を揺らした
VIVA! STAGE・6組のアクト

行きの電車で向かい側に家族連れが座っていた。聞こえてくる話の内容からしてどうやらビバラに行くらしい。20代くらいの娘さんも、そのご両親もきっとそれぞれのお目当てを観るのだろう。ビバラなら、特にこの2日目のVIVA! STAGEのようにジャンルも世代も多岐にわたるラインナップなら、きっとしっかり楽しめるんだろうな。そんなことを思いながら会場へと向かう。

2日目、全4ステージで最初に始まったVIVA! STAGEのライブ。ちょうどビバラの立ち上げ準備を始めた10年前に「すごいバンドが出てきたな、ここから時代は変わるな」、そう思わせられたというプロデューサー鹿野の紹介を受け、トップバッターを務めたのはKANA-BOON。特効の炎と大音量のジングル、そして万雷のハンズクラップに迎えられ、ドラムセットの前で向かい合ってジャーンと一発、鳴り出した切れ味鋭いカッティングと図太いベースラインは“シルエット”だ。谷口鮪(Vo&Gt)のイノセントな歌声がすーっと真っ直ぐに放たれる。お次は“ないものねだり”。小泉貴裕(Dr)を中心としたタイトながら強靭なアンサンブルの推進力が、アリーナ全体をドライヴさせていく。古賀隼斗が軽やかなギターソロを決める傍らに並び、ベースを高々と掲げる遠藤昌己(Ba)。そんな何気ないシーンに滲み出るバンド感にもグッとくる。
冒頭の人気曲連打でオーディエンスの耳目をガッチリ掌握した後、お立ち台に飛び乗った鮪の弾くヘヴィなリフで始まったのは“ディストラクションビートミュージック”。旋回する鮮やかな照明とストロボが場内を照らすが、そういえばさっきからずっと、背後にはバックドロップ代わりだろうか、どでかくバンド名のみを映して演奏している。それがなんだか「これが俺たちだ」と誇るようでかっこいい。
前日に誕生日を迎えた鮪とバンドのメジャーデビュー10周年、ビバラの10回目の開催を祝った後、新曲“サクラノウタ”の切なくも力強いサウンドを瑞々しく響かせた後は、「ここらでもうひと盛り上がりしましょうか」とグルーヴィーな演奏と人懐っこいメロディが印象的な“スターマーカー”へ。北澤ゆうほを呼び込んでラストに届けたのは“ぐらでーしょん”だった。彼女のキュートな歌声とバンドのサウンドが融合し、ポップな煌めきを帯びる。去り際、サプライズの花束を受け取って無邪気に喜ぶKANA-BOON。彼らが残してくれたのは、ここから1日、それぞれ思い思いに色んなステージへ赴くあろう観客たちを、あたたかく送り出すような余韻だった。

KANA-BOONがメジャーデビュー10周年なら、続くflumpoolは15周年。エレクトロニックなSEの中、静かに歩み出る落ち着いた登場シーンから一点、眩い光を背負って「おはよう!ビバラ会いたかったよ!」と朗らかに叫ぶ山村隆太(Vo)。そのソフトな感触の歌声に阪井一生(Gt)のコーラスとハイトーンのカッティングが寄り添う“星に願いを”を歌い終え、「はじめまして、flumpoolです!」と初々しく挨拶。2020年に出演が決まっていたもののコロナ禍を受けた開催断念で流れてしまったという彼らは、これがビバラ初登場。初見の観客も少なくない環境ながら、いくつもの広く浸透したレパートリーと、キャリアに裏打ちされたライブ力でもって自分達のペースに引き込んでいく。
尼川元気(Ba)と小倉誠司(Dr)からなるリズム隊が引っ張る重心低めのサウンドに、深めのエフェクトをかけたボーカルが色っぽく響く、ダークなダンスロックは“夜は眠れるかい?”。タイトルコールの時点で歓声と拍手が巻き起こったデビュー曲“花になれ”では、淡々とした演奏が次第と輝きを増していくのに合わせ、アリーナ中からたくさんの手が上がる。中盤には「ビバラで絶対にやりたいと思って持ってきました。コロナ禍でも少しでも心を通わせられたらと思って作りました」とライブ初披露の新曲“Magic”が演奏された。山村がアコギを弾きながら、あたたかで落ち着いたミドルテンポにジワッと染み入るグッドメロディを歌う。
「お昼ご飯の前に、僕らともうひと暴れしませんか?」「3年間ずっと心の中で叫んでたでしょ、その声を聴かせてくれよ!」とたっぷりコール&レスポンスをして場内を温めてきってから、EDMライクなアレンジが身体に直接作用する“World beats”を繰り出し、仕上げは聴き覚えのある鍵盤のイントロに沸いた“君に届け”。<たまらなくビバラが好きだ>と歌詞を変えていたように、ストレートなラブソングであると同時に、どこかこういった場における出演者と客席の関係のようでもある名曲を、メンバーみな晴れやかな表情でダイナミックに歌い鳴らしていった。

3組目のandropは、SEが消え入ると同時に“Voice”のイントロへと繋げる立ち上がり。ミラーボールが無数の光線を放つ中、飛び跳ねて歓迎するオーディエンスがサビでは一斉に「オーオオー」というコーラスで声を合わせる様子は壮観だ。鍵盤が加わるなど、原曲からアレンジが変わることで格段に豊潤さを増したその音は、破格のスケールで広大な会場を巡る。ガラッと雰囲気を変えて2曲目は“Lonely”。前田恭介(Ba)がシンセベースを弾くなど、フューチャーソウルな音像が形作られ、内澤崇仁(Vo&Gt)の「歌う」と「話す」の中間のような平熱ボーカルも良い味を出している。楽曲ごとにガラリと色を変えながら、かつそのいずれも高い完成度と解像度で届けてくれる今のandropの成熟ぶりを、この時点でまじまじと見せつけられる。
「いろいろありましたけど、今日あなたが無事生きて、この場所に来られたことが素晴らしい」と言葉に力を込めた内澤が、スマホのバックライトを点けるよう促してから、ステージ照明なしで、客席から放たれる白い光のみに包まれながら演奏したのは、美しいメロディとドラマティックな曲調を持つバラード“Hikari”。「お礼と言ってはなんですが」と、次の曲を先ほど取り出したスマホによる動画撮影OKにしてくれるのが粋である。佐藤拓也(Gt&Key)のカッティングギターに内澤がボイパを合わせるセッションから“Tokio Stranger”へと進み、伊藤彬彦(Dr)を中心とした一糸乱れぬアンサンブルで、リズムチェンジを繰り返す複雑な構成をさらっと乗りこなしてみせた。
“SuperCar”の軽やかなポップネスで、場内を聴き入るモードから楽しむモードへと塗り替え後は、「この曲を何年もずっとやりたかったんだよ」と“Yeah! Yeah! Yeah!”をドロップ。たくましい4つ打ちに乗せたダンサブルなギターチューンは、以前から彼らのライブに欠かせないピースだ。ただし、これも今やしっかりブラッシュアップされており、迫力も高揚感も当時の比ではない。初見や久々に彼らを観るという人が例外なく味わったであろう驚きと衝撃は、歓声と拍手となってandropを見送った。

リハ終わりに「みんな楽しんでいこうね、イェイイェイ」と軽い調子で呼びかけたりと、飄々として気負わない本人のテンションと裏腹に、熱い出迎えを受けたスガ シカオ。登場後の第一声は「日本一大好きなフェスに出られて、俺は幸せです」だった。
スガを中心に、ギター、ベース、ドラムに鍵盤/シンセ、女性コーラスが並ぶ6人編成でのライブは、“19才”からスタート。ドライヴするファンクロックに乗ってステップを踏みながらフリーダムに、ちょっぴりエロティックに、それほど張り上げていないのによく通るハイトーンボイスを響かせながら、何度も笑顔をのぞかせる。「知ってる人は一緒に歌ってくれよ」と、かつてKAT-TUNに歌詞提供した曲のセルフカバー(作曲者であるB'z・松本孝弘のプロデュース)、“Real Face”も披露された。ハードロッキンなギターリフ一発。縦ノリと横ノリ、隙間と重厚さのバランスが絶妙なアレンジで興奮を掻き立て、アリーナ一面がタオルをブンブン振り回して盛り上がる。お立ち台で煽りながらみせるスガの無邪気な表情は、大ベテランに対して大変失礼な表現をすると……なんだか可愛くもある。
ロック調の曲が続いた後は、スラップベースが導く80'sディスコティックな“コノユビトマレ”。会場の盛り上がりを前に「すげーな、ツアーファイナルみたいな景色だ! ありがとう!」と喜ぶスガ。ノスタルジックな香りのするAOR調の“さよならサンセット”を経て、“午後のパレード”でもしっかり盛り上がったのだが、よくよく考えたら、こういう軽やかなファンクネスと人懐っこいメロディの合わせ技という、ここ10年くらいフェスを賑わすバンドが取り入れてきたスタイルをずーっとやっているんだ、この人は。加えて、自らキメてみせたギターソロのかっこよさと言ったら!
「この曲は俺からみんなへの贈り物です。いろんな嫌なこととか辛いこと、たくさんあると思うけど。一歩一歩進んでいけば必ずゴールに近づきます」との言葉を添え、おそらく最も多くの観客が知っているであろう“Progress”を最後の最後に配し、感動的にライブを締めくくった。

アンプもドラムセットもない真っさらのステージ。BE:FIRSTの登場を告げる暗転と同時に上がった、すさまじい歓声が7人を出迎える。「VIVA LA ROCK! 全員で踊ろうぜ」。昨年の初登場以降、他の大型フェスにも出演するなど経験も実力も積み増してきた彼らの「凱旋ライブ」はまず、“Boom Boom Back”からスタートした。各メンバーのアップが映ったり、ダンスのキメがビシッと合わさったり、吐息をマイクに乗せたり。そんな一挙手一投足に大歓声が上がる様子に思わず気押されてしまう筆者はロック畑在住なので、正直に言うと普段から彼らを熱心に追っているわけではない。ジャンルレスとはいえロックフェスであるビバラの会場には、同じようなリスナーがかなりの数いたはずだが、誰を観にきたとか関係なく、全てを圧倒していくパワーに満ちたライブであることに初っ端から気付かされる。
ヒップホップなトラックに乗って、先ほどとは対照的にラフに動き回りながら代わる代わるマイクをとり、7者7様の見せ方で迫った“Milli-Billi”から、勢いそのままに“Move On”へ。「夢はいつ見たって遅くねえからな」との熱い言葉が添えられたのは“Brave Generation”。曲調が変わるごとに、いや、1曲の中でも展開が変わるたびに変幻自在のパフォーマンスが続く。どこを観ていれば良いかわからないくらい、メンバーそれぞれの見せ場が盛りだくさんだ。
パフォーマンス中の不敵な佇まいが嘘のように低姿勢で礼儀正しいMCで、出演できたことへの感謝、アニバーサリーを迎えたビバラへの祝福、そしてこれから先への決意を口にしたあと、最新曲の“Smile Again”からライブは後半へ向かう。ミクスチャーロックを思わせるトラックの“Scream”は、SHUNTO、MANATO、RYOKI、LEO、JUNON、SOTA、RYUHEIとマイクをリレーしていったり、狂気混じりのスクリームを織り交ぜたりと見どころ十分。この曲に限らず、クリーン寄り、ハスキー寄り、ハイトーン、力強いなどなど、それぞれ異なる歌声の特性を絶妙に生かした構成と見せ方が素晴らしい。そして言うまでもなく、磨き抜かれた歌もダンスもとにかくハイクオリティだ。
“Bye-Good-Bye”からの“Shining One”という象徴的な2曲まで、40分の持ち時間で実に10曲を届け切った7人。余談だが、楽屋へと戻る際にも出迎えるスタッフみんなに頭を下げていく礼儀正しさっぷりを発揮していた。出会った人を次々に惹きつけていくその魅力は、ステージの上だけにとどまらない。

10回目のビバラ2日目、世代もジャンルも多岐にわたるアーティストが立ってきたVIVA! STAGEのトリを務めるクリープハイプもまた、このステージを締めくくるに相応しい個性豊かなバンドである。無音の中登場するや、赤裸々で独白のような“ナイトオンザプラネット”の歌詞をアカペラで歌い出す尾崎世界観(Vo&Gt)。小川幸慈(Gt)の柔らかなギターの音色がジャジーなコードを奏で出し、小泉拓(Dr)の刻むシンプルな8ビートと鍵盤のフレーズが合わさればチルなグルーヴを醸すバンドサウンドとなり、語る様な調子の平坦なメロディに声色で抑揚をつけていく。歌い終え、「なんだよ畜生、どうせアウェーかと思ったら最高じゃねえか。……ありがとう」とこぼす尾崎へ向け、悲鳴のような声援が飛ぶ。
ほんの数十秒前とは別バンドのようにエッジィな音をぶつけ、早口のフレーズをシャウトしまくった“身も蓋もない水槽”、和太鼓のようなバスドラが轟き、長谷川カオナシ(Ba)が重低音を撒き散らしながら尾崎とのツインボーカルをとる“火まつり”。これまた和の香りのするイントロが大歓声を呼び、ザクザクとナタの様な切れ味のサウンドを叩きつけた“キケンナアソビ”──。ソリッドなバンドサウンドに突き抜けるハイトーン、独自な言葉選びで話し口調を使ったり韻を踏んだりするリリックという、クリープハイプの唯一性にどっぷり浸れる瞬間の連続だ。
「声出しもできるようになったから、聴きたいんだけどアレが。俺が一番聴きたいんだけど」との言葉からは、当然“HE IS MINE”が演奏された。ラスサビへ向けヒートアップしていく演奏がブレイクした瞬間、そこら中の観客が一斉に「セックスしよう!!」と叫ぶ光景はよく考えなくても異質すぎて最高である。MCでは「ずっと出してもらってて嬉しく思います。鹿野さんがメインで立つのは今回が最後だと聞いて、どうしても今日このステージでお礼を言いたいなと思って。(中略)それは当たり前にライブをやるってことです」と宣言。友達だと思っているというプロデューサー鹿野への愛とリスペクトを率直に語る。そして、何か意を決したように再び口を開き、扁桃炎を押して出演していることを明かした。「情けない」と悔しさを滲ませながらもしかし、思い切りハイトーンのサビから始まる"オレンジ"をぶっ込み、歌い切ってみせる。“イノチミジカシコイセヨオトメ”までの全ての演奏を終え、尾崎が深々と長いお辞儀をしてからステージを去るまで、徹頭徹尾、これこそがクリープハイプのライブだった。
テキスト=風間大洋
撮影=小杉歩





