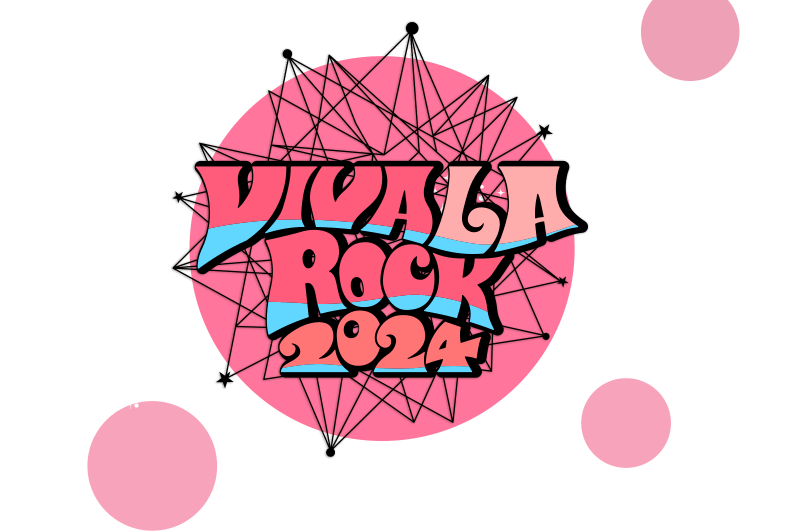総括レポート
「枠」を越え「型」を破る
CAVE STAGEの8組が示した
ビバラの自由と多様性

その年ごとの音楽シーンのカラーや、新たに興ろうとしている潮流を最も如実に映すのが、このCAVE STAGEではないだろうか。VIVA LA ROCK 2024の2日目、5月4日の顔ぶれを見渡すとバンド形態が多めだが、そのスタイルや音楽性は千差万別。いずれもある種の「尖り」を魅力に変えつつそれぞれの志向を極めながら、次代のSTAR STAGEやVIVA! STAGEを担う存在へと飛躍する可能性を存分に秘めたアクトが揃っている。

トップバッターはブランデー戦記だ。生音に近い音色のエレキギターを掻き鳴らしながら、蓮月(Gt&Vo)が気怠げに歌い出した“coming-of-age story”は淡々とした前半から、激烈な間奏を機に一気にギアを上げる。「朝早いのにこんなにたくさん観にきてくれて嬉しいです。ありがとうございます」という初々しい挨拶と、不敵にすら映る演奏中の大人びた佇まいのギャップがなんだか微笑ましい。MCもほどほどに投下された新曲では、みのりの硬質なベースを前面に押し出してグイグイ推進していく。
初期Arctic Monkeysばりのロックンロール“黒い帽子”しかり、印象的なリフで直球勝負する“Kids”しかり、ところどころ歌謡テイストも感じるウェットな良メロは、間違いなく彼女たちのストロングポイント。起伏に富んで聴き応えたっぷりなインストから“僕のスウィーティー”へと繋いだ流れでは、3ピースの演奏そのものでしっかりノせていく地力も感じさせた。ツインボーカルに近いコーラスや、良い意味で今っぽくない篭った音作りも好作用。最後のMCに送られたリアクションの大きさは、彼女たちがCAVE STAGEに詰めかけたオーディエンスをいかに魅了したかを証明していた。

開演10分前から断続的にCAVE STAGEへと集まり続ける観客の姿が、その注目の高さを物語る。2組目はNIKO NIKO TAN TANだ。クリエイティヴ・ミクスチャー・ユニットを標榜するそのスタイルは一目見た時点で他と一線を画しており、ボーカルのOchanはシンセやPCを操りながら歌い、通常のバンドの基本編成であるギターやベースはいない。サウンドの多くはヒップホップやダンスミュージックが土台となっているが、そのビートを担うのはAnabebeの叩く生ドラム。トラックミュージックの多様性とバンド音楽のダイナミズムが同居したその音で、瞬く間に場内のボルテージを上げていく。
ディスコパンクやアシッドジャズのDNAを感じるダンサブルなサウンドの“カレイドスコウプ”、和を感じさせるフレーズとバキバキのエレクトロが融合を果たした“IAI”、「知ってる人は歌ってください」と呼びかけゆったり揺らし踊らせた“水槽”。クールさとキャッチーさが当たり前のように同居した楽曲は、いずれも独特なバランス感覚を示すものだった。
つい先日にはメジャーデビューとアルバムのリリースを発表したばかりの彼ら。そこから披露された“MOOD”もまた、R&Bを思わせるウィスパー混じりの歌やメロディに、どちらかといえば縦ノリな重厚なサウンドが合わさった新基軸で、この先まだまだ上り詰めていきそうな気配が充満したライヴであった。

初っ端から凄まじいまでに分厚い音を放ちスタートした鉄風東京は、寂寞感の滲むリリックをメランコリックな歌と音色に乗せた“街灯とアパート”から、叫ぶようなタイトルコールとともに“スプリング”へと雪崩れ込む立ち上がり。たくましい8ビートが牽引する無骨な演奏と吼えるようなスタイルの歌とは裏腹に、メロディ自体はどこか優しく爽やかで、すんなりフロアに浸透していく。
溢れる思いが口をついて出る、といった様子でまくしたてる大黒峻吾(Vo&Gt)の発言は、早口具合とラウドなサウンドのおかげで半分くらいしか聞き取れないが、並々ならぬ気合いでビバラへ臨んできたこと、そしていまこの瞬間を楽しみきっていることは十二分に伝わった。かつてビバラプロデューサー・有泉智子がとあるバンドを評した「ロックバンドの原石が磨かれることなく原石のまま輝いている」という主旨の言葉に感銘を受けたことを明かした上で、自分たちはその辺に転がってる石くらいの方があなたの近くにいられる、それがカッコいいライヴしたらロマンがある、と大黒。ビート感満点の“TEARS”からラストの“21km”まで一気に突き抜けていった。ペース配分する気なんてさらさらなし。全球全力投球の清々しい姿ではっきりと爪痕を残した。

リハの段階からパンパンで物理的にも熱気を一段階上げたのはConton Candy。“baby blue eyes”から弾むようにライヴはスタートした。カラフルな音と秀逸なメロディラインを持つ新曲“アオイハル”に続いては、3声コーラスやハーモニーで魅せる陽性ポップス“ロングスカートは靡いて”。息のあったプレイを展開する楓華(Ba)と彩楓(Dr)のリズム隊を中心にタイトに引き締まったサウンドの上を、ふわりと舞うように、けれど要所ではしっかり刺してくるパンチ力も備えた紬衣(Vo&Gt)のボーカルは訴求力たっぷりだ。
ビバラには中学生の頃に観客として来たことがあるという紬衣の思い出とともに、当時や今日出番前に観たバンドから受けた「カッコいいな」「喰らったな」という気持ちを何倍にもして返したい、と投下したのは“ファジーネーブル”。キャッチーなサウンドが場内を席巻し、満員のフロアが波を打つ。「自分はライヴハウス気分でやる気はなく、一番デカいステージだと思ってやるために来た」という意気込みそのまま、フルスロットルで放った“102号室”の堂々たる音とパフォーマンス、それを後押しとばかりに突き上がった無数の拳を観る限り、「本当に一番しか狙ってない!」という彼女たちが数十m向こうにある大舞台に立つ日もそう遠くない気がする。

個人的に最も「してやられた」のは5組目に登場したALIだった。ジングルが鳴り出す頃には、既にLEO(Vo)を除く全員がステージ上にスタンバイ。その編成はLUTHFI(Ba)、CÉSAR(Gt)に加えてサポートメンバーとして名手・BOBO(Dr)、さらに鍵盤と3名のホーン隊に女性コーラス(曲によってはボーカルも)までいる豪華さで、こんなにCAVE STAGEが小さく見えるのは初めてである。みなジャケットスタイルなどドレッシーな出立ちでキマっており、さぞかしスタイリッシュなライヴになるのかと思いきや、これがとんでもなくアツかったのだ。
いや、ビジュアル面だけでなくジャズやファンクをベースにしたサウンドも、思い切りスタイリッシュではあった。だがそれ以上にアツさが漲っていた。ご機嫌なスカサウンドに乗ってモンキーダンスするLEOがひたすら「ガバガバ」と投げかけ観客が「ヘイヘイ」と応えるだけで無性にテンションの上がる“GABBA GABBA HEY HEY”、セクシーに腰をくねらせながら男女デュエットで歌うファンキーな“LOST IN PARADISE”など、どの曲もプレイ姿からして熱量と楽しさのメーターが振り切れていて、結果として極上のエンタテインメント空間が完成していた。11年目にして初登場。「歳とか関係ねえな、夢叶えるには」なんて言っていたが、もっともっと多くの耳目に届いてほしい名演だった。

2日目のビバラも気づけば後半戦。それなりに乳酸も溜まってきたであろうこのタイミングでSPARK!!SOUND!!SHOW!!がお出ましというのは、「完全燃焼せよ」というメッセージだろうか。多分そうだろう。
「良い子のみんな、前おいで」なんてタナカユーキ(Vo&Gt)は軽い調子で呼びかけるが騙されてはいけない。マッシヴな“感電!”のサウンドに乗ってチヨ(Ba)タクマ(Key&Gt)との3MCスタイルでシャウトとスクリームをお見舞いすれば、フロアは即刻カオスに。メタル色の濃い“SKIMMING ME!!”、“†黒天使†”でヘドバンを誘発したかと思えば、唐突に訪れるダンスミュージック的な曲展開ではお祭り騒ぎ。“TOKYO MURDER”ではついに169(Dr)までマイクを手にステージ上で暴れ回る。もう、なんでもあり。これがスサシの流儀。
ライヴ後半には「友達呼んでます」とさらっとゲストを呼び込み、現れたのはなんとつい先程までVIVA! STAGEに出ていたTHE ORAL CIGARETTESの山中拓也! 歓喜に沸くフロアに“SUSAORA”を投下して狂乱の渦を巻き起こす。前回のビバラ出演はコロナ禍の影響下だった彼らにとって、眼前に広がる光景は待ちに待ったものだったはずだ。そのままの勢いで“STEAL”、“YELLOW”とファストナンバーを連発して、「戦争反対」の真っ直ぐなメッセージとともに嵐のようなライヴを終えた。

オンリーワンな個性と存在感を有するアクトが揃ったCAVE STAGEの、象徴的存在と言えるのがCVLTEだろう。重々しく荘厳なSEが鳴り止むと、一瞬の静寂を置いて響き出したのはaviel kaei(Vo)の儚げな歌声。中央のお立ち台での祈るようなポーズにはカリスマ性が滲む。空間ごとぶった斬るような強烈なブレイクダウンと狂気的なダンスビートで攻めるのは“digital paranoia.”。デジタルなシーケンスや鍵盤の音色とヘヴィなバンドサウンドが絶妙に融合しており、予測不能な展開はもうプログレの域である。
繊細なフレーズと美メロがやがてアンセミックなサビへと至る“girls lie.は前半のハイライトと呼びたい名曲ぶり。空間ごと震撼させるサブベースなど低重心のサウンドに、時折鮮やかにロックギターが差し込まれる“hellsong.”を挟んでの“happy.”では、フロアにスマホライトを点灯するよう促してその光景に表情を緩ませる一幕もあった。……と、CVLTEの曲にはあらゆる要素が顔を覗かせるが、徹底して貫かれたクールな質感と美学にブレはない。「ロックなのか何なのかわからない、紛い物が紛れ込んで申し訳ないけど」なんてavielは謙遜していたが、ラストの“scorpion.”みたいなエモ色の強いアプローチなんて、ラウド好きの琴線を鷲掴むこと間違いなし。末恐ろしい若き才能だ。

「さいたまスーパーアリーナの最奥地。俺たちが普段戦ってるライヴハウスとなんら変わらねえよ。何も怖くねえ! VIVA LA ROCK 2024、2日目、CAVE STAGE、ラスボスやりに来ました」
初登場にしてステージのトリという大役を任され、そこで堂々と宣言してみせたammoの岡本優星(Vo&Gt)。3ピースの醍醐味そのものなパワフルにしてソリッド、ひと塊となって突き進むサウンドと、持ち前の言葉遊びや巧みな韻がよく聴き取れるはっきりとした発声によって歌詞に描かれる風景にリアルな息吹を与え、ストーリーテリングの役割も担う歌。1曲目の“何℃でも”から自らの強みを遺憾なく発揮し、フロア前方はたちまちモッシュピットと化す。
「俺たちの生き様の歌」と紹介された“CAUTION”では、端正な8ビートに乗せてammoというバンドの存在理由とその証明をまっすぐに歌い鳴らし、はじめに記した発言に続いては熱量むき出しの演奏で“星とオレンジ”を投下して大勢のクラウドサーファーを生む。さらにノンストップで“これっきり”へと突入すると岡本は、真裏のVIVA! STAGEを観に行った奴らを後悔させてやろう、俺らは今日しかできないライヴをしにきたんだ、と絶叫。輪をかけたファストチューン“突風”まで繰り出すなど、終盤にかけての勢いは特にすさまじかった。
アンコールは無しだと前置いた上でラストの“フロントライン”では、曲中で「ラスボスじゃない、挑戦者だ」と自らの発言を回収した岡本。STAR STAGEやVIVA! STAGEに特に強力な出演者が並ぶ時間帯だけあって、この日の場内は満員とまではいかず、正直、相当な悔しさがあったのだろう。だがその逆境をバネに繰り広げたエモーション全開のライヴは潔く、眩かった。正真正銘のラスボスとなってオーディエンスを迎え討つその日まで──。ビバラとammoの歴史は始まったばかりだ。
テキスト=風間大洋
撮影=ハタサトシ